前回の写真のチェンバロは私の愛器。
これは、フレミッシュ・タイプ・ハープシコード(英語なんでチェンバロはハープシコードとなる)で、埼玉県にお住まいの楽器製作家 柴田雄康氏が作った楽器。
フレミッシュとは、フランドル地方のという意味で、現在の北ベルギーとオランダにあたる。
ここでは17世紀、大変活発に楽器を製作した一族がいた。
ルッカース一族である。
彼らのいたアントワープは16世紀中葉に東方貿易の経路であったために、北ヨーロッパの重要な商業活動のちとなり、聖ルカ・ギルドという職業組合があり、様々な業種が組合員となり、活発なそして、かなり自由な活動をこの組合が保障をしていたようだ。
ここに、このルッカースも加入が許されていた。他には有名な画家ペーテル・ブリューゲルや、出版屋のヒエロニムス・コック等もいた。
そのような、商業組合の中で、かなり楽器を量産していたようで、また、同じギルド仲間には木版画屋もあってであろう、楽器に木版画の紙を張っている楽器が多くある。これは、量産を可能にした要因でもあろう。
そして、張られた紙の上にラテン語の格言を書くようになった。

そういうことで、再度この楽器を眺めていただこう。
蓋を開いたところに模様のように見えるのは、木版画の紙。
そして、何やら文章が書かれている・・・これが格言ある。
鍵盤上の蓋:Acta virum probant 行為は人を証明す
弦の上の蓋:Sic transit gloria mundi かく浮世の名誉は移り行く
これを眺めながら、毎日自分を戒めながら演奏するわけです・・・んな訳ないですが・・・。
後、足に注目。
この丸っこい、引き物(こけしの要領で、まわして削っていって形作るもの)。無骨に大きな丸ですね。メロン・ターンスといって、この当時のフランドルの家具の足に良くなっているものです。当然楽器の台にも使われています。私はこのまるっこいのがとても気に入っている。
以上、楽器説明でした。
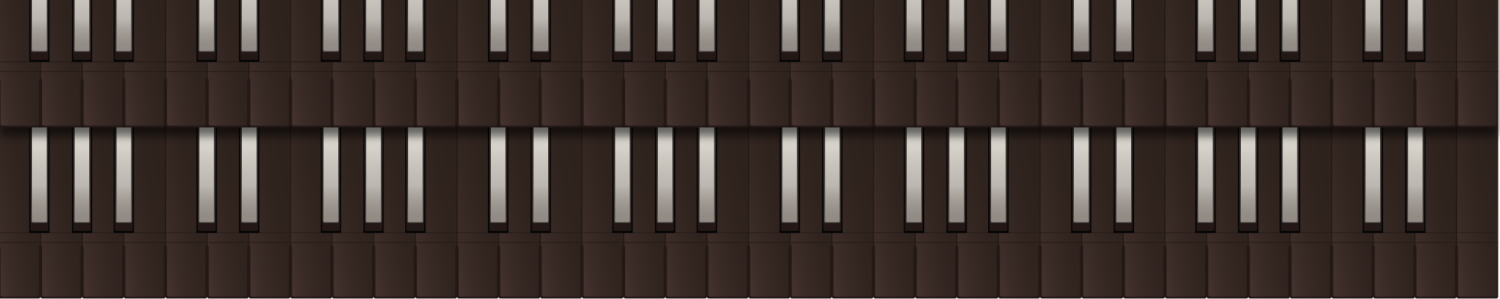
ラテン語って文化に根付いているんですよね。多くの人が未だにラテン語をすらすらっと読めて意味が言えるのは凄いなあと思います。日本では漢文をすらっと言える人は減りましたよね。
めぎさん
そうですね。漢文すらと言えない一人です。
でも、ラテン語すらすら言える日本人知ってます。でも、ちょっと変わった人です、笑。
あ、私の友人も、ラテン語バリバリのがいます。
で、やっぱりちょっと変わってます♪
めぎさん
あはは、やっぱり~